ビジネスの現場で英語が使われることが増えましたよね。
その場では理解しているふりをしてもいても間違った解釈でトンチンカンなリアクションをして恥をかきたくないですよね?
以前もよくわからない英語・カタカナ語に関する記事を書きましたが、日々働いているとまたまた???な言葉が増えてきましたのでまとめます。
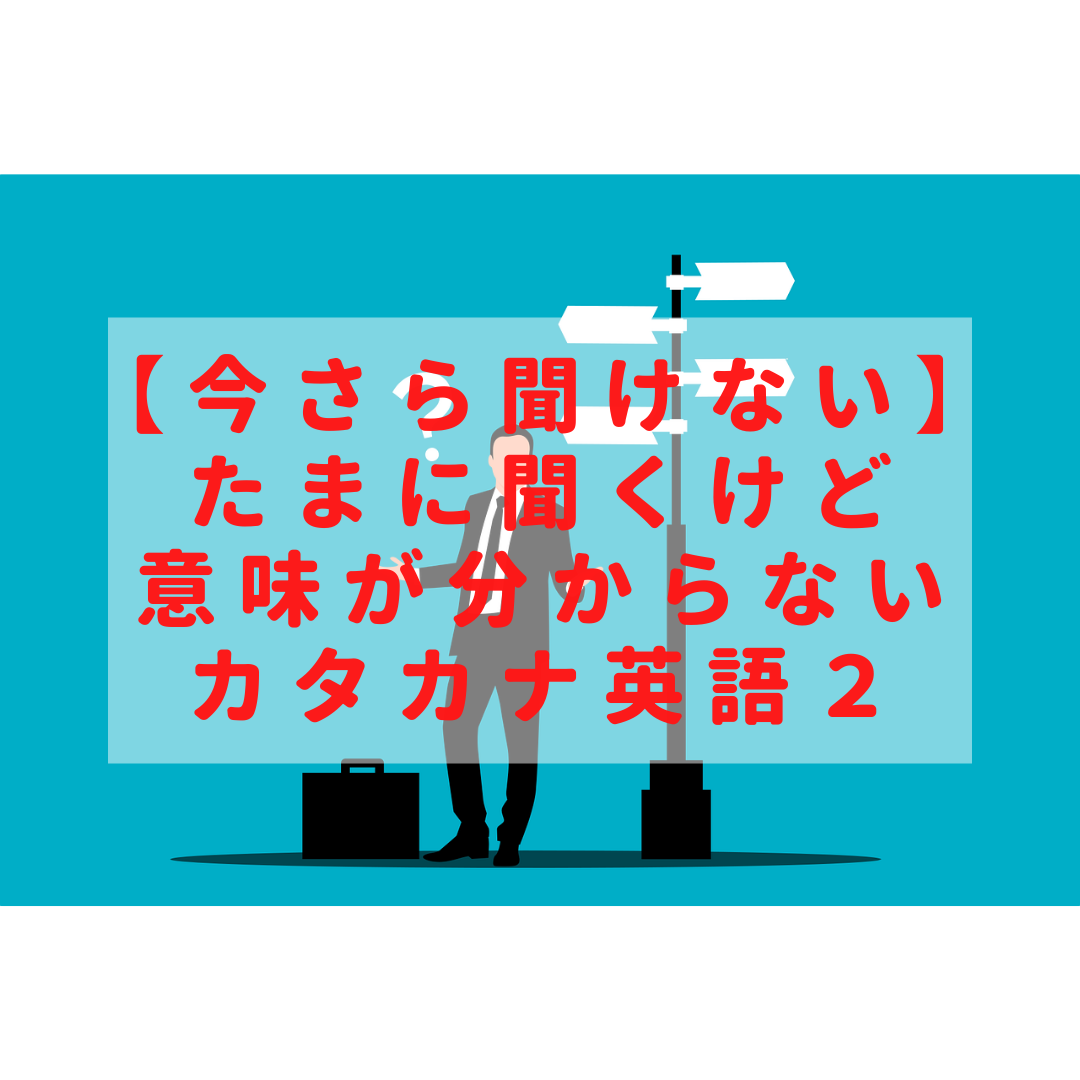
- メタ認知:Metacognition
- コモディティ化:commodity
- デファクタスタンダート:de facto standard
- DX(デジタルトランスフォーメーション:Digital Transformetion)
- Tips:ティップス
- オーソライズ:authorize
- プレゼンス:presence
- ゼネスタ:general staff
- SIer:エスアイヤー
- アグリー:agree
- まとめ
メタ認知:Metacognition
意味:メタ(meta:高い次元)と認知(cognition:認知)から生まれたとされる言葉です。
高い次元から認知するという言葉の意味するところは、高い次元から自分自身を見つめるという形で使われメタ認知能力の高い人=自分を客観視できる人という意味になります。
メタ認知能力の高い人は自分自身の状態を客観視できることから、コミュニケーション能力に優れ、目標設定や問題解決の能力に優れていると言われています。
また、メタ認知能力の高さは人間関係にも影響を及ぼすと言われており、近年ではビジネスにおける人材教育からコミュニケーションスキルまで注目されています。
メタ認知という考え方の起源としては、古代ギリシャのソクラテスと言われています。
ソクラテスの有名な言葉に「無知の知」という言葉があります。
この言葉の意味するところは「彼らは何も知らないのに知っていると思い込んでいるが、私は何も知らないということを知っている」というもので、まさに自分が認知している内容を認知している。「メタ認知」が出来ているからこその言葉になります。
使い方:「あの人はメタ認知の能力が高い」「あの人はメタ認知ができない人だね」のように使われますね。
コモディティ化:commodity
意味:コモディティはもともと日用品というような意味の言葉になります。
コモディティ化はマルクスの資本論で提唱された考え方で、市場に流通している商品がメーカーごとの個性を失い、消費者にとって値段以外に差を感じなくなってしまっている状態を指します。
要因は様々考えられますが、商品そのものに付加価値が無く価格競争に陥ってしまうとコモディティ化している状態と呼ばれます。
コモディティ化している商品はメーカー側からすると競合他社よりも安い商品を投入するしかなくなり利益が少なくなってしまいますが、消費者側からすると商品の質が均質化し価格も安くなるので購入しやすくなるという側面があります。
近年では人材市場においても他者と差別化できていない人材をコモディティ化してしまっている人と揶揄するような表現も見られます。
使い方:「あの商品はすでにコモディティ化してしまっている」というような比較的ネガティブな使われ方をするパターンが多いですね。
デファクタスタンダート:de facto standard
意味:ISO,DIN,JISなどの標準(スタンダート)を決定する機関が定めた規格ではなく、市場の競争原理のなかで「結果として事実上標準化した基準」を意味します。
デファクタスタンダートに反する言葉として標準化機関で定められた標準をデジュリスタンダート(de jure standard)と呼びます。
デファクタスタンダートが後の国際規格の土台となる場合もありますし、自社製品がデファクタスタンダードになった企業は競合他社と比較して大きなアドバンテージを得ることになります。
使い方:「新しいサービスを生み出してデファクタスタンダードになれば市場で優位にたてる」という感じですね。自分たちのサービスが基準になることで先行者利益を確保できますからね。
DX(デジタルトランスフォーメーション:Digital Transformetion)
意味:DXとは2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念となります。個々の言葉の直訳はデジタル=デジタル、トランスフォーメーション=変換となります。言葉の意味としては「進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにする」または「進化したデジタル技術が人々の生活を良いものへと変革させる」となります。
なぜデジタルトランスフォーメーションの略称がDXかというと英語圏ではTransをXと略すことが一般的だからです。
2018年5月、経済産業省は有識者会議による「DXに向けた研究会」を設置し、同年にDXレポートやガイドラインが発表されるなど注目度がましていることに加え、近年では企業の部署としてもDX推進部門が設置されるなどしています。
使い方:「これからの時代はDX(ディーエックス)の推進がカギだ」のように使いますね。
Tips:ティップス
意味:英語としての意味は①(もののとがった)先、先端 ②(山などの)頂点、頂上 ③ 先端につけるもの ④(傘、杖などの)石突き ⑤ 釣り竿の先端部 ⑥(たばこの)フィルター ⑦ 吸い口 ⑧(茶の)葉芽と多数の意味があります。
日本で使われだした時は「コンピューターで使う裏技など」を指す用語として使われ始めた言葉ですが、現在ではコンピューターに限らず「さまざまなコツや裏技」を指す言葉として使われています。
使い方:「このサービスのティップスを教えて」みたいな感じで使いますね。
オーソライズ:authorize
意味:本来の意味は「許可する」「公認する」「権限を与える」となりますが、ビジネスシーンでは転じて「関係者に認められている」という意味をメインとして以下のように使われています。
「新商品のオーソライズを取得する(新商品の正式な許可をえる)」
「部長のオーソライズを得る(部長の承認をえる)」
「ソフトのオーソライズを行う(ソフトの認証を行う)」
似たような意味の言葉に「コンセンサス」というものがありますが、コンセンサスは「意見の一致」などの意味合いがあります。
一方でオーソライズは正式な認可を得るときに使う言葉となりますが、日本の企業内でそこまで明確な使い分けをしている所は少ないかもしれないですね。
使い方:よく使われるパターンだと上司が部下に「今回の企画のオーソライズを取っておいて」のように指示をだす場面が想定されますね。
プレゼンス:presence
意味:もともとの意味は ① 存在 ② 存在感 ③ 出席 ④ 参列 ⑤同席 ⑥ 軍隊 ⑦警察の配備 ⑧ 駐屯といった意味があります。
ビジネスの場面ではある国が経済的、政治的に大きな影響力を持つことでその存在感を無視できない状況の時に使われます。
たとえば「日本では輸出入においてアメリカのプレゼンスが高い」というような使い方です。
使い方:「その商材は中国のプレゼンスが高いので中国の動向はよくチェックしておくように」というような使い方をしますね。
ゼネスタ:general staff
意味:General=一般の、普遍的な、大体のなどの意味となりますが、generalstaffは企業経営者に直属する経営者の補佐や援助をする部門。参謀、幕僚という意味になります。
企業によっては秘書室、経営企画部門、監査部門などをゼネスタ部門として括っている会社もあるようです。
使い方:上記の通り、秘書室、経営企画室などの経営層に近い部門をまとめてゼネスタ部門と呼ぶ企業があります。
SIer:エスアイヤー
意味:エスアイヤーとはSI(システムインテグレーター)を受注する会社のことです。
システムインテグレーターとは、金融システム、生産管理システム、在庫管理システムなどさまざまなシステムの要件定義⇒設計⇒開発⇒運用を行うサービスとなります。
そのSIサービスを提供している企業がSIerです。
SIerとは何をやっている会社かというとシステム関連のサービス全般ということです。
本来であれば企業は自社でエンジニアを雇用し、自社で使うシステムを開発できれば良いのですが現実的にはそのためにエンジニアを雇用し続けるよりも他社に委託した方が効率が良いのでSIerに依頼する企業が多くなります。
使い方:あの会社はSierだというような使い方になりますね。
アグリー:agree
意味:アグリーは「同意する」「賛成する」という意味の言葉となりますので、ビジネスの場で使われる時にも同様の意味で使用されています。
例えば会議の場で賛成の意思を示すさいに「アグリーです」というような使い方をします。
使い方:「私はその提案にアグリーです」というような使い方ですね。私も正直アグリーという人には一人しか会ったことないですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
日々会社で使われるカタカナ語が増えてしまいますが、知らない言葉も自分もアップデートして覚えていかなくてはならないので頑張りましょう。